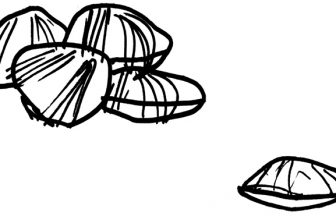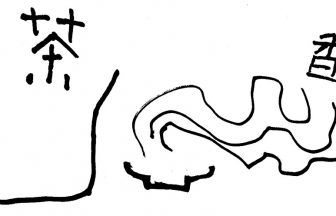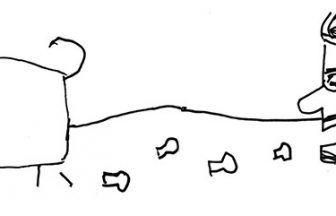1973年、今から48年前のこと。身長167㎝、体重48㎏のガリガリの、まだ幼い顔をした脇屋少年が初めて就職した日が3月24日である。同期で入社したのは15名だったと思う。中卒は脇屋友詞1人のみ。高校を卒業して入ったのが半分くらい、ほかは専門学校を卒業してからの入社だった。
入社の日。赤坂見附駅前の信号を渡ると、ピンクと白の縞模様の『赤坂東急ホテル』があり、外堀通り沿いに虎ノ門方面に向かって歩いて行くと『ホテルニュージャパン』、その横に『ナイトシアターロイヤル赤坂』があり、畠山みどりや欧陽菲菲などの顔がバーンと描かれた大きな看板を見て「都会だな!」と思い、さらに歩き進むと日枝神社にたどり着いた。大きな鳥居のふもとの桜は七分、八分咲きだったと思う。
そのすぐ傍に『山王飯店』があり、オーナーは読売巨人軍の王貞治選手の後援会長でもあった。とても大きな店で、結婚式は4、500名、レストランは150名ぐらい入れる規模だった。正面にはライオンの置物が対で鎮座し、中に入って行くと右が宴会場、左がレストラン。レストランの扉を開けると見渡す限り金と赤で、まるで竜宮城のよう。中国映画に出てくる宮廷の晩餐会でもできそうな雰囲気に驚きとめまいがしたのを覚えている。
僕は何も知らずに中国料理の調理場にポンと放り込まれ、寮生活というのを始めた。麻布十番の公園のすぐ横にある寮で、実家からは紙箪笥、ファンシーケースと布団が送られてきた。優しい先輩が多く、「困ったことがあったら何でも言いなさい」と、大人が子供を出迎えるように接してくれたことが、つい昨日のように蘇ってくるから不思議である。それが1973年3月の思い出である。長い1週間が過ぎ、同期の新入社員が勢揃いしたのは4月1日だった。
さて、15歳の少年は寮生活を2日、3日と過ごし、何が嬉しいかというとご飯がいっぱい食べられること。おかずもいっぱい食べられる。ただ、見習いは常に先輩の間で立ったまま賄いを食べる。これは嬉しくなかった(笑)。
新入りの僕の仕事は鍋洗い。毎日毎日鍋を洗う。最初の優しい先輩はどこへ行ったの!? 1カ月も過ぎると優しさはほとんど消え、「鍋の回りをよく擦れ!」「白い料理が全部黒くなるんだ!」と怒られたことが、鍋のこびりつきのように頭にこびりついている。上海料理は煮込みものが多い。煮込み料理は煮汁を強火でブワーッと煽り、煽ることでとろみが香り、それが上海料理の醍醐味である。だが、僕にとっては醍醐味どころか大迷惑である。とろみがこびりついた鍋を毎日何千枚と洗わなくてはならない。日本料理やフランス料理と違い、炒め物(白い料理)、スープから煮込みまでひとつの鍋ですべてを作るのが中国料理の技である。急いで洗うと煮込みのとろみでついたこびりつきが落としきれない。その鍋を火にかけると墨のようなものがスープに浮かんでくる…。そして先輩の怒声が飛んでくる…。
長い長い修業のスタート、いよいよ先輩のかわいがり(笑)が始まるのである。
「味の手帖」(2021年3月号掲載)
イラスト=藤枝リュウジ