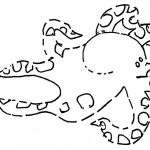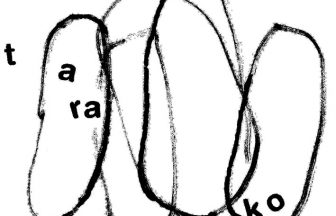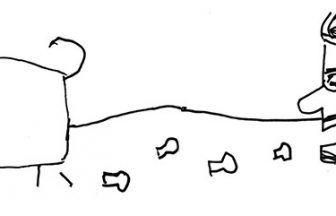子どもの頃、北海道の森町に母方の先祖のお墓があり、毎年お盆には家族で墓参りに出向いた。その帰りに毎回もらうのは、段ボールいっぱいのスルメのげそと昆布。僕たち兄弟のおやつである。昆布を口の中に頬張りじゅるじゅる噛んでいると、最初はしょっぱく、後から味がじんわりじんわりと漂う。噛めば噛むほど美味くて、お腹に入った時になぜか満たされる感覚があったことを覚えている。あの頃に感じた満足感というものを大人になって初めて勉強することになる。
遡ること13、4年前になると思うが、「うま味」についてとても詳しく、昆布を知り尽くしている味の素の山本さん、二宮さんと、昆布を見に利尻、礼文を訪ねたことがある。その時に山を2時間ほど歩いてどんぐりの苗木を植樹した。伐採が続いて丸裸になった山から、雨によって土砂が海に流れて行く。海底の岩に根を張る昆布は、砂が降り積もった状態ではしっかりと根を下ろすことができずに枯れてしまう。木が成長して豊かな森になれば、土砂の流出が抑えられ、木の養分が海に流れてくる。昆布は海水中の養分を吸収して光合成して成長する。結果的に昆布が生い茂る海中林に魚も集まってくる、と言うのである。森があればこそ魚も近づく、海を守るためには山も守らなければならない、そのための緑化事業であった。この訪問をきっかけに昆布の大切さ、美味さ、奥深さに興味を持ち、料理にも昆布をいっそう積極的に使うようになった。中国料理の上湯に昆布を加えると、鶏肉や金華ハムが持つうま味成分イノシン酸と、昆布のうま味成分グルタミン酸の相乗効果で美味しさが倍増する。
昆布が縁で色々な出会いがある。2015年にNHK「きょうの料理」で日高・えりも町を訪ねた時は、昆布漁師の川崎さんご夫妻に大変お世話になり、昆布の煮物や昆布巻きなど地元ならではの料理を教えていただいた。日高の昆布漁は7〜10月に行われるが、実際に漁が行えるのはごく限られた日数である上、年によって獲れる昆布の量も大きく変わってくるそうだ。川崎さん曰く、昆布と生きることは自然と生きることそのものなのだという。
昨年は、「夏休みこんぶ塾」という企画で再びえりも町を訪ねた。北海道新聞と味の素による、札幌在住の子どもとえりも町の子どもを対象にした企画で、地元の漁師さんの協力のもと昆布の生態を学ぶという内容である。僕も料理人として、フレンチの上柿元勝シェフ、『更科堀井』の主人堀井良教さんと共に参加し、昆布を使った料理で昆布が持つうま味を子どもたちに実感してもらった。彼らの素直な反応を見て、あらためて人が舌で感じるうま味、出汁を感じる味覚のおもしろさに気づかされた。
江戸時代には昆布漁が行われ、北前船で日本各地に運ばれていたといわれる。数百年の時を経た今、僕も昆布を通して様々な人との繋がりが生まれている。礼文島の植林から始まり、日高の昆布漁師の方々や地元のお母さん方、そして子どもたち、さらに他県の人たちへと、その繋がりはこれからも粘り強く続いて行きそうだ。
「味の手帖」(2020年8月号掲載)
イラスト=藤枝リュウジ