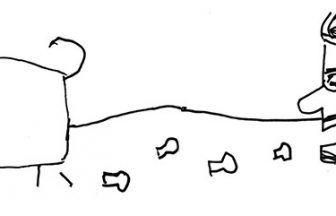その先輩は、素晴らしいユーモアのセンスの持ち主で、もちろん包丁さばきも上手で、良い先輩だなぁと思っていたが、実は違う一面もあり。
ある日、「唐辛子を掃除するからこっちに来い」と何も知らない僕を呼んだ。袋いっぱいの唐辛子のヘタを取り、種を取り出し、切り分けていく。形や色のきれいなものは炒めものなどの料理に使い、形の悪いものは辣油づくりに使われる。ヘタと種を取り出していくと少しずつ手が黒くなり、鼻が少しムズムズしてくる。「おい、友詞、鼻になにかついているぞ」と先輩に言われ、思わず左手で鼻を触ると何もついていない。まわりの皆はニヤニヤしている。おかしいな、ともう一度こすった瞬間、小鼻のあたりがカーっと熱くなり、涙がにじみ出てきた。その痛さはどんなに洗っても半日くらい取れない。あとから他の先輩に、誰もが唐辛子の洗礼を受けてきたのだと教えられた。
辛い油と書いて辣油。店の辣油づくりはすさまじく、子供がお風呂に入れるほどのボウルいっぱいにつくる。3人がかりで掃除した唐辛子と唐辛子の種に、一味唐辛子を3種類ブレンドしたもの、ねぎの青いところ、しょうが、少量の塩をボウルに入れる。水を少々ふりかけ、手ですこしずつもみほぐす。よく混ぜ合わせたら180℃くらいに沸かしてある白絞油を大きなひしゃくでジュワーっとかけていく。初めて見た時は、熱い油を辣粉にかけた瞬間、火山のように吹き出す様子に度肝を抜かれた。手ぬぐいで顔を覆い、ジュワーっと油をかけたときに木べらで混ぜるのが新米の僕の役目。煙たいし、熱いし、そのときの目の痛さ、香り、頭のてっぺんからズボンまで唐辛子の煙が染み付くくらいの辣油づくり。油を入れる度に「混ぜろ!」と言われ、必死にかき混ぜる作業は面白さ半分、目が痛くて逃げ出したくなるのが半分だったことを今でもはっきり覚えている。
油をかけ終わったら蓋をして一晩おく。次の日に蓋を開けると、なんと! 透明だった油は鮮やかな紅色になっていて、ボコボコと爆発していたような粉が全部下に沈んでいる。その上澄みのきれいなこと! 舐めてみるとすごく辛いが、香りよく豊かな風味がある。上澄みの油だけを寸胴鍋に入れ、下に沈んだ粉は別に分ける。油を吸った粉は辛い料理に使う。辛い担々麺の中には、この粉を少しときれいな赤い辣油を入れることにより、熱いスープを注いだときに香ばしさと辛さが立ち上り、ウマ辛味に変身するのである。担々麺も麻婆豆腐もエビチリも、この辣油が味の決め手になる。
辣油というのは、料理長によって香辛料の入れ方、配合、唐辛子の粉、すべて違い、店それぞれの味があり、もちろん僕の店でも一度に大量の辣油を仕込んでいる。その様子を見ると必ず先輩の顔を思い出す。そして自分の受けた唐辛子の洗礼を後輩にもやっていたことが懐かしくおもしろい。痛いが笑える、笑えるが痛い思い出話である。
「味の手帖」(2021年4月号掲載)
イラスト=藤枝リュウジ